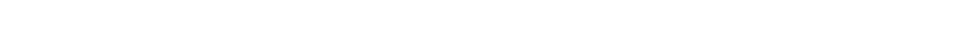みなさんこんにちは!
ブリリアント更新担当の中西です。
雑学講座~酔わない工夫~
ということで、ナイトワークの経験者が実践する「酔わないための工夫」を詳しく紹介します。
水商売の世界では、お酒を飲む機会が多くあります。キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナックなどで働く人々にとって、お客様と一緒にお酒を楽しむことは仕事の一環です。しかし、毎日お酒を飲んでいては体を壊してしまうし、酔いすぎると接客に支障をきたすこともあります。
では、水商売のプロたちはどのようにして「酔わずに飲み続ける」ことができるのでしょうか?
1. 飲む前の準備がカギ!体を守る方法
① 事前に胃を保護する(食べ物・飲み物)
お酒が体に回りやすいのは「空腹時」。そのため、飲む前に以下のような食べ物・飲み物を摂ることで、アルコールの吸収を遅らせることができます。
おすすめの食べ物・飲み物
牛乳やヨーグルト → 胃の粘膜を保護し、アルコールの吸収を遅らせる
オリーブオイル → 胃の粘膜に膜を張り、アルコールの影響を緩和
チーズやナッツ類 → 脂肪分がアルコールの吸収を緩やかにする
炭水化物(ご飯・パン・パスタなど) → 胃に負担をかけず、アルコールを分解しやすくする
これらを飲む前に少しでも摂っておくことで、酔いにくくなります。
2. 飲んでいる最中のテクニック
② お酒の濃さをコントロールする
水商売では「お客様に合わせて飲む」ことが求められますが、実際にすべてのお酒をそのまま飲んでいると、あっという間に酔ってしまいます。そこで、多くの人が行っているのが 「薄める」 という技術。
具体的な方法
お客様が目を離した隙に水や氷を足す
あらかじめ店側で薄めたお酒を用意しておく(水割り・ソフトドリンク混合)
炭酸割り(ハイボール・レモンサワー)を選び、自然に水分摂取量を増やす
特に「お客様にバレずに薄める」スキルは、長く働くために重要です。
③ こっそり「チェイサー」を飲む
チェイサー(水やお茶)をこまめに飲むことで、アルコールの濃度を下げ、体への負担を軽減します。
スマートなチェイサーの取り方
お酒を飲むふりをして、実は水を飲む
「喉が乾いた」と言って自然に水を注文する
シャンパンのグラスに水を入れておく(特にホストクラブでよく使われる技)
水を多く飲むことで、アルコールが薄まり、酔いを防ぐことができます。
④ 「吐息でアルコールを抜く」方法を活用
アルコールは呼吸でも排出されるため、意識的に深呼吸をすることで酔いを和らげることができます。
ポイント
息を深く吐き出すことでアルコールを排出
鼻呼吸を意識することでリラックス効果も得られる
外に出て新鮮な空気を吸うことで酔いが早く覚める
「少し酔ってきたな」と思ったら、ゆっくり深呼吸をしてみると効果的です。
3. 体に負担をかけない飲み方の工夫
⑤ 「飲み方」を変えて負担を減らす
お酒の飲み方を工夫することで、体への負担を減らすことができます。
プロが実践する飲み方テクニック
一気飲みをしない(ゆっくり飲む)
お酒を口に含んで少し時間を置いてから飲み込む(吸収を遅らせる)
ストローを使わず、グラスで飲む(ストローはアルコールの吸収を早めるため)
「ゆっくり飲む」ことを意識するだけで、酔いにくくなります。
⑥ カクテルを選ぶ時の工夫
お酒の種類によって、酔い方が変わります。
酔いにくいお酒の選び方
カクテルよりも焼酎・ウイスキーの水割りを選ぶ(糖分が少なく、悪酔いしにくい)
甘いカクテルは避ける(糖分が多いとアルコールの吸収が早まる)
炭酸系のお酒は飲みすぎないようにする(炭酸はアルコールの吸収を促進する)
同じ量を飲んでも、お酒の種類によって酔いやすさが変わるため、自分の体質に合うお酒を見つけることが大切です。
4. 酔いを早く覚ますための方法
⑦ 酔いを早く抜くための裏技
もし「飲みすぎた」と思った時には、以下の方法を試してみましょう。
酔いを早く抜く方法
温かいスープを飲む(味噌汁・コンソメスープが特に効果的)
クエン酸を摂る(レモン・梅干し)
軽く運動する(ストレッチ・散歩)
ツボ押し(手のひらの「合谷(ごうこく)」や、足裏の「湧泉(ゆうせん)」)
「明日も仕事があるのに、飲みすぎた…」という時には、こうした対策をすると回復が早くなります。
まとめ:水商売のプロは「飲み方」を工夫している!
水商売の人が酔わないためには、以下のような工夫が必要です。
酔わないためのポイント
飲む前に胃を保護する(牛乳・オリーブオイル・炭水化物)
お酒を薄めたり、チェイサーを活用する
深呼吸やツボ押しでアルコールを抜く
甘いカクテルや炭酸系を避け、酔いにくいお酒を選ぶ
飲みすぎた時の対策を知っておく(味噌汁・クエン酸・運動)
お酒と上手に付き合うことができれば、水商売の仕事を長く続けることができます。無理をせず、健康的に働けるよう工夫していきましょう!